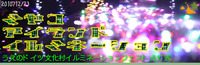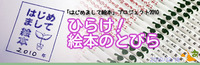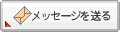2011年01月21日
掃海艇来宮~第46掃海隊「ししじま」「くろしま」
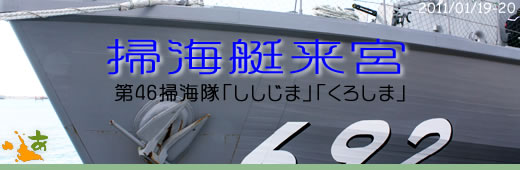
平良港第一埠頭に見慣れぬ灰色の艦艇が接岸しています。海上自衛隊佐世保地方隊隷下、沖縄基地所属の第46掃海隊の「ししじま」と「くろしま」の2艇の掃海艇が、広報活動の一環として来宮し、一般公開されました。自衛隊の艦艇の来訪ということで、意見としてはさまざまにあるかと思いますが、宮古も国境の島であることを改めて考えさせられる寄港である一方、普段なかなか見ることの出来ない船に興味はつきませんでした。

この船はどこから来たのか?。掃海艇ってなんだろう?。など、いろいろと調べてみたらなかなか面白いことが判りました。まず、この2挺が所属する沖縄基地で、県内で唯一の海上自衛隊海上部隊の基地(海自航空部隊は那覇にもある)で、沖縄県うるま市の与勝半島の先端にあります。地理に詳しい人なら与勝の先端はホワイトビーチ(米海軍の軍港)だと気づかれるかと思いますが、海自の沖縄基地は事実上、このホワイトビーチと一体化しているそうです。

今回、平良港に寄港したMSC-691「ししじま」(10番艦)とMSC-692「くろしま」(11番艦)は、すがしま型掃海艇と呼ばれる掃海艇で、2挺の所属する第46掃海隊には、もう1艇「あおしま」が所属しており、通常の任務には3艇で行動するそうです。
艦艇のサイズば全長54メートル、全幅9.4メートル、基準排水量510トンと小型なのは、掃海艇の主な任務が機雷の除去で、磁気機雷対策として船体が金属でなく木造の艦艇だからです。このすがしま型を発展させた後継艇、ひらしま型も3艇ほど建造されましたが、今後は船体がFRP製のえのしま型にとってかわられる事になり、最後の木製の掃海艇となります(諸外国では早くからFRP製の船体が導入されいました)。

安全に航海が出来る海にするのが掃海艇の仕事なので、主な武装は船首にある20mm機関砲が一門だけ。それも対空向けに弾幕を張るためではなく、ほぼ静止した機雷を撃って除去するために使われるのだそうです。船尾には機雷除去のための機雷処分具(有線式の小型潜水艇のような形をしています)や、ボートで接近して潜水作業するための各種装備がいろいろとあります。
艦名の「ししじま」は鹿児島県の北西部の不知火海にある獅子島が由来。一方の「くろしま」はてっきり八重山の黒島かと思ったら、長崎県の佐世保の西方にある同名の黒島が命名の由来でした(乗船記念のパンフより)。

船内の見学はシンプルな艦橋を初め、士官室、食堂、トイレや風呂など、生活空間も見ることが出来ましたが、艦橋の下にあったCIC(戦闘指揮所/Combat Information Center)は、日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法により、許可なきものの立ち入り禁止と明記されていました。
通路にドコモの衛星公衆電話(艦橋の屋根にアンテナがある)があり、その下に携帯電話一時保管庫というロックのかけられるボックスがありました。職務中は携帯禁止なのでしょうね。

艦橋後方にある大きな鐘。その昔は艦内に時間を知らせる為などに使われていたもので、現在は現役の設備ではなくモニュメント的なものになっているそうですが、それぞれの艦名が就役した年月とともに記されています。
他にもいろいろと船ならでは、自衛隊ならではのこまかな不思議で面白いものがあって興味がつきませんでした。
自衛隊の船ということで、一部では「怖い」という声も聞きましたが、案内をしてくれた隊員の皆さんは、なれないホスト役をこなしている感はあるものの気さくな方ばかりで、掃海艇という危険な職場で頑張っているのだと感じました。
[関連資料]
海上自衛隊ギャラリー/すがしま型掃海艇
自衛隊図鑑/すがしま型掃海艇
[関連記事]
みなとフェスタ2010 in 平良港
(文+写真+編集:モリヤダイスケ)
Posted by あんちーかんちー編集室 at 09:00│Comments(0)
│あんちーな特集