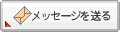2009年01月20日
綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan_top2.jpg)
今回は「あんちーかんちー」誌上、初の続きモノとなった「綾道マップ」の完結編です。
◆前回のまでのあらすじ~2009/01/16掲載(前編はコチラ)
宮古島市役所をスタートして旧市街地に眠る、歴史と文化を辿るウォーキングマップ「綾道マップ」を、ふらりふらりと訪ね歩き、第14ポイントの「人頭税石」までたどり着きました。
『平良 綾道マップ(ピサラ アヤンツマップ)』
2001年に旧平良市の総務部企画室が製作展開した、島の言葉で「美しい道」と名づけられた「綾道マップ」は、平良の古くからの中心地として平良五箇(ピサラグカ)と呼ばれる、西里、下里、荷川取、東仲宗根、西仲宗根の五村を、歴史・文化をテーマにして巡るウォーキングマップです。
それではお待ちかねの完結編のスタートです!
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan_map2.jpg)
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan12.jpg)
「綾道マップ」のルートは「人頭税石」まで続いた海沿いから離れて、第15ポイントの「湧川マサリャ御嶽」へ向かいます。道路沿いに続く家並みの中にある茂みがそれでした。ここに看板がなければ、見逃しそうなくらい、ただの茂みにしか見えません。
『マサリャという漁師が釣り上げたエイが、女性に変身して二人は夫婦に。その後、竜宮に招かれて瑠璃壷を土産にもらって帰り、マサリャは裕福になるも、隣人に秘密を打ち明けてしまい、壷は白鳥となって飛び去ってしまった』
この御嶽に伝わる伝説を、かいつまんで荒すぎるあらすじで紹介してみましたが、世界各地にある竜宮伝説が宮古島風の物語としてあったことが興味深いです。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan13.jpg)
御嶽の脇の細道を抜け、どこかゆったりとした時間が流れているような里道を進んでゆくと、雑木林の中に大きな鳥居と、コンクリートで綺麗に整地された御嶽が現れました。第16ポイント「ウプムイ御嶽」のようです。
ところが手元にある「綾道マップ」のパンフレットでは、「ウプムイ御嶽」にナンバリングがありません(今回の地図と前回の地図を見比べて下さい)。パンフレットの16番には次の「カーニ里御嶽」で、17番がルートを外れて表通りにある「荷川取村番所跡」とされています。ルートの流れから見て、看板の地図が正しようですが、せっかくなので幻の17番の「荷川取村番所跡」も訪ねてみましょう。
ということで、いったんルートを外れて表通りへ出てみると、「荷川取村番所跡」はあっさり見つかりました。道端の標柱だけというかなり拍子抜けする展開ですが、村番所には公共機関としての機能の他にも、機織場や染め場も設けられていたそうです。畑の奥に御嶽があるなど、それなりの雰囲気が残っているような気もしました。っと、無理矢理まとめておきましょう。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan14.jpg)
さて、ルートに戻って第17ポイントの「カーニ里御嶽」へ向かいましょう。この御嶽はとても珍しく、福木などが生い茂る趣のある御嶽を中心に、北・東・南の三方向に参道を持っているのです。低い石垣に挟まれた参道は素晴らしい造りをしていました。
中でも東側の参道はブロック塀に向かって伸びており、なんとも不思議なことになっています。「綾道マップ」のルートにもなっているので、この参道を進んで行くと、ブロック塀のところで石垣は終わていましたが、塀に沿って細道が続き、家の間をすり抜けて、元の通りへと抜けるという面白いルートになっていました。恐らくは家を建てる際に、このような形に変わってしまったのでしょう。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan15.jpg)
緩い坂を登って降りて、複雑に入り組んだ大和井(ヤマトガー)交差点へ。この交差点はいくつもの旧道が残っており、旧道マニア垂涎の不思議な構造になっています。
まずは歩道脇から崖下に見える大きな丸い石組みの井(ガー)、「ウプカー」。かつては牛馬用の井戸でしたが、水道の普及や牛馬の減少などからいつしか忘れられ、埋もれてしまいましたが2004年に復元されました。
道路を渡って第18ポイントの「大和井」へ。ここは国の史跡にも指定されており、かつては役人専用の井戸として門が設置され厳重に管理されていたそうです。庭園のような敷地を奥へと進むと、ガジュマルの根元に見事な石組みで作られた降り井戸(ウリガー)があります。
個人的な話ですが、なぜか「大和井」で撮影をすると、シャッターが切れなかったり、ピンがぼけていたり、ハレーションがおきたりすることが多く、不思議な相性を持っています。もしかしたら、前世が役人じゃないので、井戸に断られているのかもしれません(笑)。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan16.jpg)
ふたたび道路を渡って向かい側の細い一方通行の坂を登ります。
実際に現地を踏破して気づいたことですが、「綾道マップ」だけで巡るには、判りづらいルートがしばらく続きます。これはイラストマップの弱点でもあるかと思いますが、「綾道マップ」はちょっと省略をしすぎているようです。
ちなみに、「島AP」のイラストマップは、地形図を元に現地調査で補足したものからイラストマップにおこしているので、地図としての正確さには自信があります。
時折、進行方向に悩みながら細道を選んで進んでゆくと、左手に第19ポイントの「ンーヌ主御嶽」と、右手に「保里遺跡」と書かれた標柱が現れました。
「保里遺跡」の「保里」は宮古の島言葉読みした、第20ポイントの「フサティ御嶽」と解読し、小径を登るとガジュマルの木の下に、香炉が置かれた御嶽がありました。パンフレットの解説にも14世紀頃の西仲宗根の首長、保里天太の居城跡と伝えられているところが御嶽とあったので、ここで間違いないでしょう(案内が不足しているので類推からポイント認定しました)。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan17.jpg)
順列がひとつ飛びましたが、反対側の第19ポイントの「ンーヌ主御嶽」に行ってみましょう。なぜ飛んだかというと、ルート上から「ンーヌ主御嶽」は見えているのですが、御嶽の入口が斜面下側にあって回り込まないと中へ入れないからなのでした。
宮古口(みゃーくふつ)読みの「ンーヌ主御嶽」を漢字に直すと「芋の主御嶽」と書きます。宮古神社の境内に建てられてる「産業界之恩人記念碑」にも記されている砂川親雲上旨屋を祀ったもので、甘藷(サツマイモ)を沖縄に持ち帰った、あの野國總管よりも前に宮古島に甘藷をもたらした人物。もしもこの人が爆発的に甘藷を普及させていたら、嘉手納の總管祭はなかったかもしれません。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan18.jpg)
「ンーヌ主御嶽」をあとにして、少し緩い坂を登り切ると住宅地へと分け入ります。このあたりの「綾道マップ」は省略がききすぎている上に、案内標識もないので、初めての人は注意しながら進んでください。
やがて住宅地の中に公園が現われます。脇の歩道を抜けると第21ポイントの「船立堂」に到着です。ここは船の神様なのだろうと思っていたら、「農具神兄カホドノ 妹シラクニヤスツカサ」と石碑に書かれていました。この兄妹が船で島になかった鉄器をもたらし、鉄製の農具を作って反映をもたらしたといういわれがあります(かなり抜粋してます)。
この「船立堂」のある住居表示は宮古島市平良字西仲宗根となるのですが、実は道を挟んだ西側は宮古島市平良字東仲宗根となります。ここでは東に西仲宗根、西に東仲宗根と東西が逆転しているのです。ちょうどこのあたりから旧・平良公民館付近の崖の上(海沿いにある墓街道の崖)まで東仲宗根が張り出しているので、こんな現象が起きています。ただ、この東西を磁北ではなく、東西平安名を結ぶ宮古島的な東西に方角にすると、偶然なのかもしれませんが、ほぼこの逆転現象が見られなくなるのです。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan19.jpg)
西仲宗根から東仲宗根エリアに移動して表通りへ出ると、早速、小さな交差点の角にある第22ポイントの「ユーラジ御嶽」に着きました。この御嶽は東仲宗根の番所跡でもあるそうですが、コンクリートに囲われた御嶽にはそんな雰囲気はまったく感じさせません。それよりも御嶽の隣にある住宅の壁に直に描かれた化粧品の看板の方が気になってしまいました。なんとなく気になって調べて見たら、エコナックという大正時代に創業したレースの製造会社(何度か社名変更をしており、絵麗奈という時代もあった)の化粧品製造する子会社、ラフィネの商品エコナージュを、楽天市場で販売するのがエレナでした。ネット専売のようなのですが、なぜこんなところに看板を?
脱線はここまでにして先に進みましょう。現在、ちょうどここが市場通りから続く拡幅工事の最先端になっています。以前は、島の北部をエリアとしている八千代バスのターミナル(仮ターミナルで営業中)や、公設北市場(2007年2月に閉場)がありましたが、ちょっと殺風景な雰囲気になってしまいました。
そんな片隅に勢いよく茂る木々があります。ここが第23ポイントの「仲屋金盛ミャーカ」。ミャーカは墓のことで、ここには仲宗根豊見親のあとを継いで頭職についた、仲屋金盛豊見親(なかやかにもりとぅゆみゃ)が眠っているようです。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan20.jpg)
ただ、この仲屋金盛豊見親は、島の南部(友利・砂川・新里・宮国とあるので砂川間切?)で人望も厚く善政をしていた金志川豊見親をねたみ、だまし討ちにして殺害。この事件に怒った首里王府は仲屋金盛豊見親に自害を命じ、間接統治の豊見親制を廃してしまう。これによって宮古島は王府による直接統治へと変わり、本格的な王府の支配下に置かれてしまうことなるのでした(大嶽城の変)。簡単にいうこと、この人の短絡的な暴挙で島の歴史が、大きくチェンジしてしまったってことでしょう。
次のポイントは24番なのですが、ひとつ飛ばし第25ポイント「外間御嶽」が目の前にあるので、先にこちらに行ってみます。この御嶽は元々、公設北市場の脇にひっそりとあったのですが、閉鎖された市場と同様に道路拡張によって移転改築されていました。なんでもこの御嶽は、その昔はそれなりに大きなものだったようなのですが、市街地の形成に伴う敷地の縮小や、移転改築を何度か経ているようで、どうもそういう運命にある御嶽のようです。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan21.jpg)
道路拡張で交差点の雰囲気もずいぶんと変わってしまいましたが、まだまだ健在のなんでもそろう仲宗根スーパーの横目に、第24ポイントの「忠導氏仲宗根家(ちゅうどうじなかそねけ)」へ向かいましょう。
仲宗根豊見親に始まる宮古の名家のことらしく、いくぶんハイカラな雰囲気の門扉と表札がありました。カギのかかった門扉の中を覗いてみると、数メートルほどの立派な福木の並木と正面にシャコ貝とヒンプンが見えました。水字貝でなくシャコ貝が置かれていることに謎は残りますが、なかなか趣のある場所でした。惜しむらくは奥が庭になっているようで、その全貌を見ることはかなわなかった点です。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan21-1.jpg)
第25ポイントは先に回ってしまったので、第26ポイントへと進みましょう。広くなって大きく変貌した道路を電気店の辻まで進むと、角に「綾道マップ」には描かれていない御嶽がありました。どことなく22番の「ユーラジ御嶽」に似た雰囲気がある、名もなき謎の御嶽を曲がって脇道へ入ると、すぐに第26ポイントの「仲屋マブリナ御嶽」への案内板がありました。
「仲屋マブリナ御嶽」は細い路地の奥におくゆかしくたたずんでいました。この御嶽は先に紹介した仲屋金盛豊見親の娘のものらしいです。父の罪科により首里王府に召し使われるも、王の目に留まり寵愛をうけ懐妊するが、宮女たちの嫉妬をかって帰郷。しかし、その途中でも、船頭の卑しい振る舞いや暴風にあい、多良間島へと漂着して失意のまま息絶えたという、父の因果が娘にふりかかった悲劇の物語があるそうです。それにしてもさすがに字名も仲宗根だけあって、仲宗根豊見親に繋がる史跡が、この界隈は本当に多いです。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan22.jpg)
いよいよ「綾道マップ」もラストスパートです。表通りを経由して住宅が立ち並ぶ細い路地に進みます。奥まで進んだら、宮古島市立北小学校の校庭に出てしまいました。授業中なので子供たちの姿はありませんでしたが、ここまで堂々とオープンにされていると、かえって校庭に踏み込み辛いですね。
さて、第27ポイント「尻間御嶽」はこの細道から路地に曲がった先にあります。げれど、奥はどう見ても道ではなく建物が建つ、ひと様の敷地の様子。「綾道マップ」のルートもここを突っ切るように描かれているので、ここはともかく進むしかありません。
建物のある敷地の裏手の駐車場に「尻間御嶽」がひっそりと鎮座していました。この建物は沖縄県の宮古支庁の旧庁舎で、老朽化から空港近くの新庁舎へ移転。その後、那覇地裁平良支部や宮古地区合併協議会事務局などが利用していましたが、築45年以上経過しており、耐久度調査で危険建築物とされ、また、補強や取壊しにも多額の費用がかかることから、現在は空き家状態のままとなっています。
この旧支庁舎は文化歴史をテーマとした「綾道マップ」に組み込めるほど、まだ長い歴史を刻んではいませんが、旧・琉米文化会館(現在の市立図書館)などのように、今は価値を見逃されがされている近代遺産は、いずれは保存していくべきものもあるのではないかと考えるのですが(旧空港ターミナルや下里公設市場など、すでに失われたものも多いのですが)、スクラップ&ビルドな都市計画なども絡んでくるので、今後の情勢に注目しておきたいと思います。
![綾道マップ[宮古島逍遥]×[島AP] 完結編](http://img04.ti-da.net/usr/akmiyako/ayan23.jpg)
いよいよラストの第28ポイント「住屋遺跡」です。旧支庁舎の通路を抜け、スタート地点であった宮古島市役所の向かい側にやってきました。半ば空き地状態になっているため、駐車場のような扱いになっており、車の間をすり抜けていかないと、まったく遺跡の説明板を見ることが出来ません。
この駐車している車が、不法なのか合法なのかは不明ですが、これでは見たくても思うように見れず残念でなりません。もっとも、このポイントの見どころは遺跡なので、この荒地の中に遺跡がどのように保存されているのかも、草の生い茂ったこの状況では、残念ながらうかがい知ることも出来ませんでした。
最後はちょっとケチもついてしまったような感じもありましたが、無事に「綾道マップ」はここでゴールとなりました。予想以上に面白い、歴史と文化を巡るウォーキングマップ「綾道マップ」、観光コースとしても手軽に楽しめるのでオススメです。
ちなみに、この「綾道マップ」を歩くと、距離が約3.5キロあり、時間にして約50分ほど、消費カロリーが90キロカロリー消費されるとの案内されているのですが、今回は取材しながらだったこともありるので参考記録ですが、auの無料アプリ「Run&Walk」を使って計測してみたら、距離5.4キロ、時間102分24秒、消費カロリー251キロカロリーにもなっていました。このペースでは平均速度が3.1キロ/h、平均ペースは18分57秒/hと、ウォーキングとはいい難い遅さになっていました。
今回、歩いた北コース(マップにはそう記されています)以外にも楽しめるコースがいくつもあれば、身近に歴史や文化にふれながら、地域に親しみながら学ぶこともでき、観光資源としても活かせるのではないでしょうか。手前味噌ではありますが、「島AP」の活動がこんな風に繋がったら本望かもしれません。
(文+写真+編集:モリヤダイスケ)
Posted by あんちーかんちー編集室 at 09:00│Comments(0)
│かんちーな企画