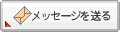2010年11月19日
島の本棚~ほんのむしぼし~Vol.001

書店で気になる本がある。買えど読めない本がある。書棚で眠る本がある。ひっそり並ぶ本がある。
・・・と、昭和の歌謡番組のナレーションのように、突然始まった「島の本棚」の新シリーズ(SEASON4)。“島のコトノハ”にこだわるセレクター『jurim(ゆりむ)』が、家の本棚から選んでみた、お勧め本をご紹介します。今回は、読むほどに、人間や、地域への愛情が感じられる3冊です。
※ ※ ※
あかねちゃんのふしぎ

文化活動に「宮古島乙女系」というジャンルがあるとすれば、この童話集の著者・もりおみずきさんは、まさにその“乙女系”女子のひとつの到達点のような方です。
高校の国語教師をしながら、コツコツと書きためた児童文学をコンクールなどに投稿し始めた、もりおさん。1996年、本書の表題作ともなった作品「あかねちゃんのふしぎ」で、沖縄の児童文学の登竜門ともいえる「ふくふく童話大賞の奨励賞を受賞したのを皮切りに、旺盛な創作意欲で、次々と作品を世に送り出してきました。
本書には、琉球新報児童文学賞や、ふくふく童話大賞受賞作など11作品が収められています。きっとタイトルのイメージどおり、可愛らしいお話ばかり・・・と思いきや、題材として取り上げられているのは、ある時期一大ブームを巻き起こした「たまごっち」や、中東の戦地に生きる子どもたちの過酷な運命など、決して甘くはない現実を見据えた、作者のまっすぐなメッセージが込められています。
また、児童劇団によって上演もされた戯曲「希望―子供たちの人頭税物語」では、子供たちの目線でとらえた近代の宮古島が、いきいきと描かれています。登場人物の会話の、なんと優しく美しく力強いことか。ぜひ、未読の方は、この本を手にとってみてください。
ニャーツ方言(フツ)

平良の市街地から東のほうに広がる東川根地区(おおむね、旧NTT・東交番・宮古病院のあたりから、北中・東小・東保育所の付近)は、その昔「ニャーツ」と呼ばれていました。本書はそのニャーツ出身の上地慶彦さんが、昔から地域で使われてきた方言や言い回しを辞典形式にまとめたものです。
まえがきによれば、著者が若い世代と共に集う中で、自分が何気なく使う方言が珍しがられることに気づき、なんとか書き残し役立ててほしいと思い立ったそうです。
実はこの本、私が上地さんに結婚式の仲人をお願いした時、友人たちと共同で執筆した「読めば宮古!(さいが族著/ボーダーインク刊)」の話になり、上地さんから「じゃあこの本も読んでごらんなさい」といただいたもの。同じ宮古島でも世代や地域によって見聞きしたこと、触れてきた文化はとてもさまざまで、興味深いエピソードもいろいろあります。
ただ、宮古の人の気質として、普段のお話はとても面白いのに、文章にすることには気後れする人が多いのではないでしょうか。気負いなく何かを書くというのが苦手というか・・・。ですから、こうして先輩方の昔の暮らしが垣間見える本は案外貴重なのです。
例えば「フギャム」の項をみると、「【いら蛾の幼虫】背中に針をもち刺されると痛い。短気の最たるものはフガマスフギャムといわれる。」などなど、味のある表現があちこちに(フガマス=小言が多く、口うるさい人)。
※本書は宮古島市立図書館などで閲覧することができますので、機会があればぜひ!。
てぃだぬ花 ~宮古・伝承の女性たち~

旧平良市役所が、男女共同参画行政の一環として刊行した本で、2003年に発刊された地域女性史「時代(とき)を紡いで~宮古の女性たち」に続く姉妹編です。
「時代を紡いで」が、近代~現代に活躍した実在の女性たちを取り上げたのに対し、本書は、中世から近世に至るまでの歴史上・伝説上の女性の物語集です。「平良市史」(平良市史編纂委員会編)や、「宮古史伝」(慶世村恒任著)などの歴史書をベースに、宮古にゆかりのある女性の書き手たちが、いまの言葉で、子供たちにも分かりやすいように物語をリライトしています。
宮古の歴史に名を残したリーダーたちの出自をたどっていくと、久松出身の「長井の里の真氏(モース)」という女性に行き当たります。おおよそ、彼女の生きた中世時代から始まる女性12人の物語は、それぞれに興味深いです。男顔負けの働きをしながら非業の死を遂げた下女ザラモイ、女傑姉妹として知られるアフガマ・クイガマ、故郷を離れ宮古で寂しく命を絶った鬼虎の娘、などなど・・・。
また、資料編は、宮古島の歴史に登場する人々の人物相関図や、本編で紹介しきれなかった伝承の女性ミニ事典、年表など盛りだくさん。郷土史研究者の故・平良新亮さんや、宮古民謡の指導者である平良重信さんのインタビューも見逃せません。
美しい表紙画を手がけたのは美術教師の平良ヒロ子さん。装丁は、ブックデザインの第一人者である宮川隆さん。・・・というふうに、執筆者から挿絵担当者に至るまで、宮古出身の方々が尽力した一冊です。
本書は宮古島市働く女性の家「ゆいみなぁ」で購入することができます。また、各小中学校や公立図書館にも所蔵されています。
[書籍データ]
「あかねちゃんのふしぎ」
もりおみずき ボーダーインク
発刊日 2003年7月10日
ISBN 4-89982-045-3
「ニャーツ方言(フツ)」
上地慶彦 私家版
発刊日 1993年11月10日
「てぃだぬ花(ぱな)~宮古・伝承の女性たち~」
平良市総務部企画室・男女共同参画室 平良市
発刊日 2005年3月
[島の本棚] バックナンバーはコチラ
Season1 「島の本棚~宮古島を読む」
myklibvo1/2009年3月~7月隔月掲載 全三回
Season2「島の本棚~Read Or Dreams」
沖縄教販宮古店/2009年9月~2010年1月隔月掲載 全三回
Season3「島の本棚~NIGHT OF GOLD」
密牙古文化部/2010年4月~2010年10月不定期掲載 全四回
(文+写真:jurim 写真+編集:モリヤダイスケ)
本書には、琉球新報児童文学賞や、ふくふく童話大賞受賞作など11作品が収められています。きっとタイトルのイメージどおり、可愛らしいお話ばかり・・・と思いきや、題材として取り上げられているのは、ある時期一大ブームを巻き起こした「たまごっち」や、中東の戦地に生きる子どもたちの過酷な運命など、決して甘くはない現実を見据えた、作者のまっすぐなメッセージが込められています。
また、児童劇団によって上演もされた戯曲「希望―子供たちの人頭税物語」では、子供たちの目線でとらえた近代の宮古島が、いきいきと描かれています。登場人物の会話の、なんと優しく美しく力強いことか。ぜひ、未読の方は、この本を手にとってみてください。
ニャーツ方言(フツ)

平良の市街地から東のほうに広がる東川根地区(おおむね、旧NTT・東交番・宮古病院のあたりから、北中・東小・東保育所の付近)は、その昔「ニャーツ」と呼ばれていました。本書はそのニャーツ出身の上地慶彦さんが、昔から地域で使われてきた方言や言い回しを辞典形式にまとめたものです。
まえがきによれば、著者が若い世代と共に集う中で、自分が何気なく使う方言が珍しがられることに気づき、なんとか書き残し役立ててほしいと思い立ったそうです。
実はこの本、私が上地さんに結婚式の仲人をお願いした時、友人たちと共同で執筆した「読めば宮古!(さいが族著/ボーダーインク刊)」の話になり、上地さんから「じゃあこの本も読んでごらんなさい」といただいたもの。同じ宮古島でも世代や地域によって見聞きしたこと、触れてきた文化はとてもさまざまで、興味深いエピソードもいろいろあります。
ただ、宮古の人の気質として、普段のお話はとても面白いのに、文章にすることには気後れする人が多いのではないでしょうか。気負いなく何かを書くというのが苦手というか・・・。ですから、こうして先輩方の昔の暮らしが垣間見える本は案外貴重なのです。
例えば「フギャム」の項をみると、「【いら蛾の幼虫】背中に針をもち刺されると痛い。短気の最たるものはフガマスフギャムといわれる。」などなど、味のある表現があちこちに(フガマス=小言が多く、口うるさい人)。
※本書は宮古島市立図書館などで閲覧することができますので、機会があればぜひ!。
てぃだぬ花 ~宮古・伝承の女性たち~

旧平良市役所が、男女共同参画行政の一環として刊行した本で、2003年に発刊された地域女性史「時代(とき)を紡いで~宮古の女性たち」に続く姉妹編です。
「時代を紡いで」が、近代~現代に活躍した実在の女性たちを取り上げたのに対し、本書は、中世から近世に至るまでの歴史上・伝説上の女性の物語集です。「平良市史」(平良市史編纂委員会編)や、「宮古史伝」(慶世村恒任著)などの歴史書をベースに、宮古にゆかりのある女性の書き手たちが、いまの言葉で、子供たちにも分かりやすいように物語をリライトしています。
宮古の歴史に名を残したリーダーたちの出自をたどっていくと、久松出身の「長井の里の真氏(モース)」という女性に行き当たります。おおよそ、彼女の生きた中世時代から始まる女性12人の物語は、それぞれに興味深いです。男顔負けの働きをしながら非業の死を遂げた下女ザラモイ、女傑姉妹として知られるアフガマ・クイガマ、故郷を離れ宮古で寂しく命を絶った鬼虎の娘、などなど・・・。
また、資料編は、宮古島の歴史に登場する人々の人物相関図や、本編で紹介しきれなかった伝承の女性ミニ事典、年表など盛りだくさん。郷土史研究者の故・平良新亮さんや、宮古民謡の指導者である平良重信さんのインタビューも見逃せません。
美しい表紙画を手がけたのは美術教師の平良ヒロ子さん。装丁は、ブックデザインの第一人者である宮川隆さん。・・・というふうに、執筆者から挿絵担当者に至るまで、宮古出身の方々が尽力した一冊です。
本書は宮古島市働く女性の家「ゆいみなぁ」で購入することができます。また、各小中学校や公立図書館にも所蔵されています。
※ ※ ※
[書籍データ]
「あかねちゃんのふしぎ」
もりおみずき ボーダーインク
発刊日 2003年7月10日
ISBN 4-89982-045-3
「ニャーツ方言(フツ)」
上地慶彦 私家版
発刊日 1993年11月10日
「てぃだぬ花(ぱな)~宮古・伝承の女性たち~」
平良市総務部企画室・男女共同参画室 平良市
発刊日 2005年3月
※ ※ ※
[島の本棚] バックナンバーはコチラ
Season1 「島の本棚~宮古島を読む」
myklibvo1/2009年3月~7月隔月掲載 全三回
Season2「島の本棚~Read Or Dreams」
沖縄教販宮古店/2009年9月~2010年1月隔月掲載 全三回
Season3「島の本棚~NIGHT OF GOLD」
密牙古文化部/2010年4月~2010年10月不定期掲載 全四回
(文+写真:jurim 写真+編集:モリヤダイスケ)
Posted by あんちーかんちー編集室 at 09:00│Comments(0)
│島の本棚