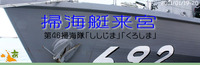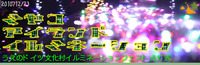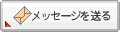2009年04月14日
明和の大津波-その時宮古は-
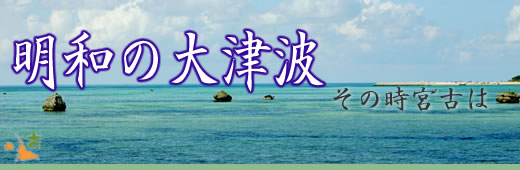
1771年4月24日(明和八年三月十日)午前8時頃、マグニチュード7.4の地震が発生。震央は石垣島の近海で、俗に云う「明和の大津波」を引き起こし、石垣島を中心に先島諸島各地に甚大な被害をおよぼしました。
震央により近い石垣島の被害は凄まじく、津波が島を横断したと云われており、石垣島だけで8439名もの死者を出しました。その後も飢餓や伝染病などの二次災害的な死者も加わり、八重山の人口は地震前の三分の一まで減少しました。壊滅的な打撃を受けた石垣島では、明和大津波遭難者慰霊なども作られ、津波の痕跡や資料からさまざまに研究がされています。
勿論、津波被害のあった宮古にも、「大津波で打ち上げられた巨岩」と云われている遺構はありますが、震央からやや遠かったり、八重山ほどの大災害(とはいっても2548名の犠牲者がでている)にならなかったからなのか、津波の資料にも乏しい上、研究もあまりなされていません。本当に巨岩を打ち上げるほどの大津波が宮古にもやってきたのだろうか、という緩い疑問が今回のテーマが始まりでした。
それでは噂に聞く、「明和の大津波」が起きた、その時を紐といて見ましょう。

[1] 明和の大津波の大きさ
まず、津波を生み出した地震について考察してみます。
九州の南から台湾にかけ、点々と島々が連なる南西諸島、その島々に添うようにして南東側には琉球海溝があります。この琉球海溝は深いところで7000メートルほどもあり、南東方向のフィリピン海プレートが、北西側のユーラシアプレートに下に潜り込んでいます。また、琉球海溝と同様に南西諸島の北西側には沖縄トラフ(海溝よりも浅い窪み)があり、このトラフはその谷を広げるように離れようとしています。つまり、乱暴にいえば南西諸島は、ユーラシアプレートから分離して、琉球海溝に引きずり込まれようとしているのです。
あまり沖縄には地震が起きないといわれていますが(実際、地震保険などの危険度ランクも低い)、大きな地震が発生していないだけで、プレートの境界線にある地震国ニッポンですから、小さな地震は無数に発生しています(逆に言えば、明和クラスの地震がしばらく起きていないということにもなる)。
明和の大津波を起こした地震の震央は、北緯24.0度東経124.3度、石垣島の南南東40km付近であったと推察されていますが、最近の調査では石垣島と多良間島の間にある、石垣島東断層の活動によるものだったとも研究発表されています。いずれにせよ、石垣島近海で発生した大地震が大津波を引き起こしたのでした。
 資料によると、その波高は最大で石垣島で85.4メートルにも達したとありました。これは国内島嶼での津波被害が赤裸々に報道された、1993年の「北海道南西沖地震」で奥尻島を襲った、30.6mを遥かに上回るサイズです(以前、実際に奥尻島を訪れた時、最大の津波が到達した場所を見たことがありますが、それはもう見上げる遥かな高さでした)。また、本州での最大波高が観測された1896年の「明治三陸地震」でさえ38.2mであり、記憶に新しい2004年にM9.3(史上二番目の記録)をマークし、観測史上最悪の226,566名もの死者を出した「スマトラ島沖地震」で発生した津波でさえ、波高は34mほどであったと云われていますので、明和の大津波は、史上、類を見ない高さの津波だったことになります。
資料によると、その波高は最大で石垣島で85.4メートルにも達したとありました。これは国内島嶼での津波被害が赤裸々に報道された、1993年の「北海道南西沖地震」で奥尻島を襲った、30.6mを遥かに上回るサイズです(以前、実際に奥尻島を訪れた時、最大の津波が到達した場所を見たことがありますが、それはもう見上げる遥かな高さでした)。また、本州での最大波高が観測された1896年の「明治三陸地震」でさえ38.2mであり、記憶に新しい2004年にM9.3(史上二番目の記録)をマークし、観測史上最悪の226,566名もの死者を出した「スマトラ島沖地震」で発生した津波でさえ、波高は34mほどであったと云われていますので、明和の大津波は、史上、類を見ない高さの津波だったことになります。しかし、そもそも当時は地震計などあるはずもなく、古事に記録された記述からM7.4という震度も算出されたということで、津波の高さを体験した人物の主観から記録されたとも考えられ、最近の研究によると津波の高さは30メートル程度だったと考えられているようです。

[2] 宮古島への津波被害
明和の大津波による宮古諸島への被害は、宮古島の南部を中心とした、友利・砂川・新里・宮国・池間・前里・伊良部・仲地・佐和田・塩川・仲筋・水納の12集落におよんだと記録されていました。尚、来間島の集落は高台にあって人的被害を免れた。水納島は津波で洗われてすべてが流失した。無人だった下地島は人的な被害はないなど、集落の成り立ちなどから被災状況もさまざまだったようです。
友利・砂川・新里・宮国の四つの集落は特に被害が大きく、集落の維持が不可能なことから、津波後に伊良部や池間島から移住させ、海岸に近い被災した旧集落から程近い高台へ、新たに集落を築いたそうです。そして旧集落は元島(むとぅすま)と呼ばれ、往時を偲ぶ御嶽などが今も残されています。
現在の友利・砂川・新里・宮国の集落の位置は、概ね標高が50メートル程にあり、旧集落のあった元島の標高は20メートル前後にありました。記録によると宮古島を襲った明和の津波の波高は、12~3丈(1丈=10尺、1尺=0.303メートル)とあり、およそ36~40メートルと換算することができますが、この計算式に使った尺貫法は今に伝わる明治に制定された尺で換算したものです。現在は日本の元号を用いて明和の大津波と云われていますが、乾隆(けんりゅう)三六年の津波と、清(中国)の元号が使われている資料の存在などから、当時の沖縄の政治状況を考えると、中国(清)の単位が使われて可能性が高いとも云われており、清の1尺は0.36メートルで換算しなおすと、43~47メートルと更に波高は高くなり、津波は新しい集落となる高台まで迫る勢いとなります。
もしも、これが本当であるならば、あくまでも比較計算値ですが、集落が高台にあって人畜に被害がなかったといわれている来間でも、島そのものの最高所が47メートルですから、波をかぶっている計算になります。
石垣島での波高が30メートル程と考えられていること。多良間島での調査(打ち上げられた珊瑚と琉球石灰岩の違いによる時代測定の結果)も18メートル程度と算出されていること。下地島には木泊村という集落が16世紀頃まであったとされ、この村は津波で壊滅したという記録があること。遠浅の佐和田の浜に点在する岩は津波で運ばれて来たといわれているが、湾の入口は石垣島とは逆の北を向いていること。また、過去二千年の間に大津波が三度あったと伝わっていることなどを踏まえると、津波岩として名高い下地島の巨岩、帯岩(高さ約12.5メートル、周囲約60メートル。岩のある標高は15メートルほど)は、本当に明和の大津波で打ち上げられた岩なのか疑問を感じざるを得ません。文字通りその真実は誰も見てはいないので、伝えられている伝承を信ずるほかないのですが。。。
尚、この津波で亡くなった宮古の人たちは、与那覇集落の西、池の崎(東急リゾート奥)に合葬され、現在は御嶽となっています。

[3] 宮古島での地震活動
明和の大津波を引き起こした地震の他にも、宮古諸島で起きた地震や津波の記録は意外にも沢山あり、どうやら定期的に島は揺れているようです。
1667年(寛文7年) 洲鎌村で水田が陥没する大地震。
1686年(貞享3年5月) 石垣が崩れる地震。
1696年(元禄9年6月) 拝殿や寺院などの石垣が崩壊。
1706年(寛永3年) 地震で死者が出る。
1771年(明和8年) 明和の大津波。
1836年(天保7年4月) 10数回の地震があり、中には石垣の崩れる地震も。
1842年(天保13年4月) 10数回の地震が発生。多良間でも観測される。
1868年(明治元年) 南東で地鳴がして地震発生。石垣が崩れ鳥居が落ちるも人畜被害はなし。
1898年(明治31年9月) 石垣島西北西沖地震。宮古八重山で家屋半壊、山崩れあり。
1938年(昭和13年6月) 宮古島北北西沖地震。1メートル強の津波。平良港桟橋で帆船が流失被害。
1958年(昭和33年3月) 石垣島北東沖地震。宮古で死者1名、重症1名、軽症2名の被害。
1960年(昭和35年5月) チリ沖地震の津波が宮古にも襲来。
※球陽、宮古史伝、理科年表、各地震被害報告書より抜粋。
2008年4月28日02時32分頃、宮古島近海でM5.2の地震(震度4:宮古島 震度2:多良間島 震度1:石垣島、西表島)が発生し、気象庁が一般向けの緊急地震速報の情報提供が開始されてから(2007年10月1日)、初めての緊急地震速報として発表されました。
実際に携帯電話の地震速報サービスで緊急地震速報を受信しましたが、速報よりも早く島は大きく揺れていました(後に情報が技術的に間に合わないことが指摘される結果を生む)。幸い、この地震では津波を含み被害は特にありませんでした。
周期的に宮古島の北方でM5クラスの地震が発生する活動が認められているそうですが、大きな被害をおよぼす可能性は低いものといわれています。地理的にプレートの境界付近に位置しており、明和以前にも大地震・大津波が発生している記録もあることから、大きな地震が発生する可能性は充分にあります。地震対策、津波対策を今一度、確認しておく必要があると感じました。もっとも、実際に石垣島を襲った明和の大津波級の85.4メートルもある津波が襲ってきたら、宮古島の最高所は114メートルしかないので、まったく逃げ場などありませんけれどね。

津波が起きた4月24日が近づいて来たので、宮古島は津波よけを願う伝統祭祀「ナーパイ」が上比屋山(ウイピャーヤマ)で行われたり、石垣島でも明和大津波遭難者慰霊祭が開かれるようで、今回の「明和の大津波」について色々と探ってみたのですが、どうも成果が足りずに不完全燃焼で、お見苦しい大いなる自由研究の域を抜けませんでした。
[参考資料]
新版 宮古史伝 (慶世村恒任 著)
琉球大学理学部 中村衛研究室HP
木村政昭ホームページ
宮古島地方気象台
石垣島地方気象台
(文+写真+編集:モリヤダイスケ)
Posted by あんちーかんちー編集室 at 09:00│Comments(0)
│あんちーな特集