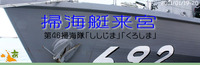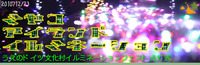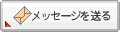2010年03月30日
TSUNAMI 1771-続・明和の大津波-

八重山での現地取材を通し、そこから見えてくる宮古を自由研究するシリーズ「やいま from みゃーく」。第一弾は「ゲンキのミナモト~3人のゲンキ君~」として、宮古では今や絶滅危惧種となっているゲンキ君を比較。第二弾は前後編の大作でお送りした「坂の上の船 -水平線の彼方にあるもの-」(前編・後編)では、久松五勇士の謎に迫ってみました。そして今回お届けするシリーズ第三弾は、2月末に起きた沖縄本島沖地震と、チリ大地震の津波襲来を振り返るとともに、「地震と津波」ついて明和の大津波の自由研究(続編)をお届けしたいと思います(明和の津波の第一弾はコチラ)。
◆ ◆ ◆
まだ記憶に新しい、2010年2月27日午前5時31分頃、本島近海で発生した震度5弱(糸満市:マグニチュードは6.9)を記録した地震。そしてそれに呼応して起きたような南米チリの大地震(日本時間の同日15時34分、マグニチュード8.8)によって列島を襲った津波は、県内にも大きな衝撃をもたらしました。
本島近海の地震では津波こそありませんでしたが、世界遺産に指定されている勝連城の城壁が崩れ落ちるなどの被害も発生。本島で震度5以上の地震が発生したのは1909(明治42)年以来、実に99年ぶりだったこともあり、ほとんどの人が始めて体験する大きな揺れでした。また、翌日、太平洋を隔てて起きたチリ地震による津波が来るという全国的な大規模な報道に、県内では218248人が避難対象となり、海上交通も乱れるなど県民の生活に大きな影響が出ました。幸いなことに県内の津波被害は軽微で、最大の津波も宮古島市平良港での50センチを記録したにとどまりました。

しかし、よくよく考えてみると恐ろしいことです。地球の裏側から津波がやってくるというスケールの凄さもさることながら、気象庁で観測された県内最大の津波の高さが平良港で記録されたとろにあります。
南米チリの位置は宮古島からはおおよそ南東の方向にあり、島の南東端となる東平安名崎あたりを襲った津波は、ぐるりと島を回り込み、池間大橋や来間大橋をくぐって、さらには伊良部島との狭い間を抜けて平良港にたどり着いているのです。
確かに津波は地形の影響を受けて増幅されることは知られていますが、より大きな津波が宮古島を襲った場合のことを考えると、もっと強く危機感を持たねばならない事態が、そこにはあると感じたのでした。
実際、琉球大学理学部 中村衛研究室の聞き取り調査(本島で実施)では、沖縄市泡瀬で93センチを観測(湾内など地形による局地的に高くなった模様)したそうす。
もっとも、観測機器が平良港(平良港湾事務所が置かれ、港湾法上の重要港湾に指定されている)にしかなく、東平安名崎にやって来た津波は数値化されていませんので、厳密なことはいいきれないかもしれませんが、最高地点でも100メートルちょっとしかない島なので、地球規模の厄災の前にはひとたまりもないのは事実でしょう。
 さて、話は本題の「明和の大津波」へと移ります。まずは以前、「明和の大津波-その時、宮古は-」と題して、明和の大津波の宮古での被害状況などについて自由研究を掲載しましたが、その際、この津波で亡くなった宮古の人たちを与那覇集落の西にある池の崎へ合葬した御嶽があると記しましたが、その時点では御嶽までたどりつくことが出来ていませんでしたが、先日、ついにその御嶽と貴重な記録資料となる石碑を実際に見ることが出来ました。
さて、話は本題の「明和の大津波」へと移ります。まずは以前、「明和の大津波-その時、宮古は-」と題して、明和の大津波の宮古での被害状況などについて自由研究を掲載しましたが、その際、この津波で亡くなった宮古の人たちを与那覇集落の西にある池の崎へ合葬した御嶽があると記しましたが、その時点では御嶽までたどりつくことが出来ていませんでしたが、先日、ついにその御嶽と貴重な記録資料となる石碑を実際に見ることが出来ました。
場所はマリンロッジマレア北側にある耕作地の奥、ほぼ人跡未踏のうっそうと茂った斜面を登ったところに、津波の死者を弔う石碑が静かにたたずんでいました(正直、ここにたどり着くには山刀などの装備が必要です)。
石碑には「乾隆三十六年三月十日大津波 宮国新里砂川」という文字が読めます。宮古では約2500名の津波による死者が出たそうですが、津波被害だっただけに、どれだけの遺体がここに安置されたのかは定かではありません。
また、石碑に刻まれた年号が日本の「明和」ではなく、「乾隆(けんりゅう)」で記されていることにも注目しておきたいと思います。「乾隆」は清(中国)の元号(1771年・明和8年)なので、小さな海洋通商国家である琉球王府が、中国の大きな影響をうけていることを垣間見ることが出来ます。ということは「明和の大津波」という呼称は、日本人が後からつけたものなのでしょうか。新たな謎が生まれてしまいました(大津波の石碑の位置)。
 続いては明和の大津波で最も甚大な被害を受けた石垣島に移りましょう。その規模や被害などについては、琉球大学理学部 中村衛研究室の「1771年八重山地震津波(明和の大津波)」に詳しいので、そちらを参考していただくとして(動画シミュレーションは必見です。また、八重山だけでなく宮古や多良間についても書かれています。ちなみに多良間はほぼ全域を津波が襲ったようです)、石垣市内での津波の痕跡を訪ねてみました。
続いては明和の大津波で最も甚大な被害を受けた石垣島に移りましょう。その規模や被害などについては、琉球大学理学部 中村衛研究室の「1771年八重山地震津波(明和の大津波)」に詳しいので、そちらを参考していただくとして(動画シミュレーションは必見です。また、八重山だけでなく宮古や多良間についても書かれています。ちなみに多良間はほぼ全域を津波が襲ったようです)、石垣市内での津波の痕跡を訪ねてみました。
石垣市大浜の津波石(つなみうふいし)。石垣島の内陸にまで津波が押し寄せる入口なった宮良湾(ほぽ震央に向かって開けた湾)の西端部の海岸近くにあり、大浜小学校南側の公園に誇らしげに木々をはやして、どっかりとそこに居座っています。津波岩の大きさとしては下地島の帯岩をひと廻り小さくしたくらいでしょうか。岩の脇に階段が設置され、頭頂部は御嶽になっていました(つなみうふいしの位置)。
当時の村々の被害率を見ても、宮良湾東側にある白保村の98パーセントを筆頭に、宮良村86パーセント、大浜村90パーセントとこの地域はほぼ全滅状態で、津波の圧倒的な破壊力の前には無力であることを思い知らされます(被災率について)。
ちなみに石垣島島内で他に被害の大きかった地域は、島の北東部の伊原間村が87パーセント。安良村が96パーセントだったそうです。規模の小さかった安良村は津波よって人口が21名まで減り、その後、移民によって村の再興をはかるも1912(明治)年に廃村となってしまいました(前出のシミュレーション動画でもこの地域はかなりの波高を見せています。旧安良村のおおよその位置)。
 次は、明和の大津波の慰霊碑が宮良台地(宮良集落北方)にあるとの少ない情報を元に、軽井沢倶楽部ホテルの北側周辺の畑の中を探索。道という道をしらみつぶしに走ること小一時間、周囲を畑に囲まれた小さな森の中に、ようやく目的の慰霊碑を発見しました(直前の入口にブリキの看板があらぬ方向を向いたまま打ち捨てられいた)。
次は、明和の大津波の慰霊碑が宮良台地(宮良集落北方)にあるとの少ない情報を元に、軽井沢倶楽部ホテルの北側周辺の畑の中を探索。道という道をしらみつぶしに走ること小一時間、周囲を畑に囲まれた小さな森の中に、ようやく目的の慰霊碑を発見しました(直前の入口にブリキの看板があらぬ方向を向いたまま打ち捨てられいた)。
「明和大津波遭難者慰霊之塔」1983(昭和58)年に建立された(建立当時の写真)。碑文には「午前八時ごろ大地震があり、それが止むと石垣島の東方に雷鳴のような音がとどろき、間もなく外の瀬まで潮が干き、東北東南海上に大波が黒雲のようにひるがえり立ち、たちまた島島村村を襲った。波は三度もくりかえした」と当時の凄まじい津波の様子が記されていました。結果的に島の人口が3分の1まで減少するという未曾有の大災害を語り継ぐ慰霊碑は、今や大きな繁栄を遂げた平穏な石垣の街を、宮良の丘の上から静かに見下ろしていました(地図は文末を参照)。
 海洋地質学者・地震学者の木村政昭・琉球大学名誉教授によると、独自の「時空ダイアグラム」理論で先日(2月27日)の本島近海地震を的中させたそうです(2011年±2:M7.0)。しかも、2009年8月5日の宮古島南方沖(M6.5/宮古島 震度4)、2010年2月7日の波照間島南方沖(M6.6/石垣島 震度3)、2010年3月5日の台湾南部(M6.4)などの発生も予想して的中させたそうです。
海洋地質学者・地震学者の木村政昭・琉球大学名誉教授によると、独自の「時空ダイアグラム」理論で先日(2月27日)の本島近海地震を的中させたそうです(2011年±2:M7.0)。しかも、2009年8月5日の宮古島南方沖(M6.5/宮古島 震度4)、2010年2月7日の波照間島南方沖(M6.6/石垣島 震度3)、2010年3月5日の台湾南部(M6.4)などの発生も予想して的中させたそうです。
木村教授の研究では、東海地震(富士山の噴火も)は2011年(±4年)に、東南海地震は2050年頃に、2012年(±3年)には東京直下地震がおこると予想されていました(木村教授の私的な作業仮説として、M6.5以上を予測)。
しかし、木村教授が的中したという地震以外にも沖縄近海(台湾~奄美)では、M6以上の地震が6回ほどおきていますので、まだまだ予知100パーセントというのは難しいように思われますが、これはとても興味深い研究です。
 また最新の調査よると、これまで大規模な地震が起きる可能性が低いとされていた沖縄にも、大地震が発生する可能性の高い、プレートの歪みをためる固着域が本島南方の琉球海溝で発見されました。分析をおこなった琉球大学理学部 中村衛准教授ら研究チームは、この海溝沿いで発生した八重山地震(明和の大津波)の痕跡から、石垣島の南方にも別の固着域が存在する可能性も判明(沖縄沖に巨大地震源 岩板境界、ひずみたまる構造 沖縄沖に大地震の巣/M8級の可能性:asahi.com)。
また最新の調査よると、これまで大規模な地震が起きる可能性が低いとされていた沖縄にも、大地震が発生する可能性の高い、プレートの歪みをためる固着域が本島南方の琉球海溝で発見されました。分析をおこなった琉球大学理学部 中村衛准教授ら研究チームは、この海溝沿いで発生した八重山地震(明和の大津波)の痕跡から、石垣島の南方にも別の固着域が存在する可能性も判明(沖縄沖に巨大地震源 岩板境界、ひずみたまる構造 沖縄沖に大地震の巣/M8級の可能性:asahi.com)。
琉球海溝は太平洋側フィリピン海プレートが、琉球列島が乗っているユーラシアプレートに沈み込もうとする、静岡県から四国沖に連なる東海・東南海・南海の地震と同じプレート境界にあたり、木村教授が予測する、2019年(±4年)に沖縄本島近海でM7.3~7.7規模の地震予知にも、大きな信憑性が増したような気がします。
果たして、2020年に開催される第32回夏季オリンピック(ロンドンの次のリオデジャネイロの次のオリンピックですが・・・)を無事に観戦することは出来るでしょうか?。
[明和の大津波]
1771年4月24日(明和八年三月十日)午前8時頃、マグニチュード7.4の地震が石垣島の近海で発生。地震によって発生した巨大津波は、石垣島では85.4メートルにも達したといわれている。
[資料]
琉球大学理学部 中村衛研究室(明和の大津波、本島近海地震、チリ地震津波など資料豊富)
木村政昭ホームページ(地震の発生予知図あり)
八重山の明和大津波 日本近海での歴史上最大級津波災害(pdfで判りやすい資料)
日本の地震活動/沖縄県に被害を及ぼす地震及び地震活動の特徴(沖縄県)[フレームあり]
石垣島の日本一・世界一その3 津波の波の高さ(読み物としても面白い石垣市による資料集)
「バリ石」は「津波石」 伊原間海岸/八重山毎日新聞オンライン(津波石の話題)
石垣島歴史の道を行く2 安良越地を歩く(旧安良村へのレポート)
[関連記事]
明和の大津波-その時宮古は-
(文+写真+編集:モリヤダイスケ)
南米チリの位置は宮古島からはおおよそ南東の方向にあり、島の南東端となる東平安名崎あたりを襲った津波は、ぐるりと島を回り込み、池間大橋や来間大橋をくぐって、さらには伊良部島との狭い間を抜けて平良港にたどり着いているのです。
確かに津波は地形の影響を受けて増幅されることは知られていますが、より大きな津波が宮古島を襲った場合のことを考えると、もっと強く危機感を持たねばならない事態が、そこにはあると感じたのでした。
実際、琉球大学理学部 中村衛研究室の聞き取り調査(本島で実施)では、沖縄市泡瀬で93センチを観測(湾内など地形による局地的に高くなった模様)したそうす。
もっとも、観測機器が平良港(平良港湾事務所が置かれ、港湾法上の重要港湾に指定されている)にしかなく、東平安名崎にやって来た津波は数値化されていませんので、厳密なことはいいきれないかもしれませんが、最高地点でも100メートルちょっとしかない島なので、地球規模の厄災の前にはひとたまりもないのは事実でしょう。
 さて、話は本題の「明和の大津波」へと移ります。まずは以前、「明和の大津波-その時、宮古は-」と題して、明和の大津波の宮古での被害状況などについて自由研究を掲載しましたが、その際、この津波で亡くなった宮古の人たちを与那覇集落の西にある池の崎へ合葬した御嶽があると記しましたが、その時点では御嶽までたどりつくことが出来ていませんでしたが、先日、ついにその御嶽と貴重な記録資料となる石碑を実際に見ることが出来ました。
さて、話は本題の「明和の大津波」へと移ります。まずは以前、「明和の大津波-その時、宮古は-」と題して、明和の大津波の宮古での被害状況などについて自由研究を掲載しましたが、その際、この津波で亡くなった宮古の人たちを与那覇集落の西にある池の崎へ合葬した御嶽があると記しましたが、その時点では御嶽までたどりつくことが出来ていませんでしたが、先日、ついにその御嶽と貴重な記録資料となる石碑を実際に見ることが出来ました。場所はマリンロッジマレア北側にある耕作地の奥、ほぼ人跡未踏のうっそうと茂った斜面を登ったところに、津波の死者を弔う石碑が静かにたたずんでいました(正直、ここにたどり着くには山刀などの装備が必要です)。
石碑には「乾隆三十六年三月十日大津波 宮国新里砂川」という文字が読めます。宮古では約2500名の津波による死者が出たそうですが、津波被害だっただけに、どれだけの遺体がここに安置されたのかは定かではありません。
また、石碑に刻まれた年号が日本の「明和」ではなく、「乾隆(けんりゅう)」で記されていることにも注目しておきたいと思います。「乾隆」は清(中国)の元号(1771年・明和8年)なので、小さな海洋通商国家である琉球王府が、中国の大きな影響をうけていることを垣間見ることが出来ます。ということは「明和の大津波」という呼称は、日本人が後からつけたものなのでしょうか。新たな謎が生まれてしまいました(大津波の石碑の位置)。
 続いては明和の大津波で最も甚大な被害を受けた石垣島に移りましょう。その規模や被害などについては、琉球大学理学部 中村衛研究室の「1771年八重山地震津波(明和の大津波)」に詳しいので、そちらを参考していただくとして(動画シミュレーションは必見です。また、八重山だけでなく宮古や多良間についても書かれています。ちなみに多良間はほぼ全域を津波が襲ったようです)、石垣市内での津波の痕跡を訪ねてみました。
続いては明和の大津波で最も甚大な被害を受けた石垣島に移りましょう。その規模や被害などについては、琉球大学理学部 中村衛研究室の「1771年八重山地震津波(明和の大津波)」に詳しいので、そちらを参考していただくとして(動画シミュレーションは必見です。また、八重山だけでなく宮古や多良間についても書かれています。ちなみに多良間はほぼ全域を津波が襲ったようです)、石垣市内での津波の痕跡を訪ねてみました。石垣市大浜の津波石(つなみうふいし)。石垣島の内陸にまで津波が押し寄せる入口なった宮良湾(ほぽ震央に向かって開けた湾)の西端部の海岸近くにあり、大浜小学校南側の公園に誇らしげに木々をはやして、どっかりとそこに居座っています。津波岩の大きさとしては下地島の帯岩をひと廻り小さくしたくらいでしょうか。岩の脇に階段が設置され、頭頂部は御嶽になっていました(つなみうふいしの位置)。
当時の村々の被害率を見ても、宮良湾東側にある白保村の98パーセントを筆頭に、宮良村86パーセント、大浜村90パーセントとこの地域はほぼ全滅状態で、津波の圧倒的な破壊力の前には無力であることを思い知らされます(被災率について)。
ちなみに石垣島島内で他に被害の大きかった地域は、島の北東部の伊原間村が87パーセント。安良村が96パーセントだったそうです。規模の小さかった安良村は津波よって人口が21名まで減り、その後、移民によって村の再興をはかるも1912(明治)年に廃村となってしまいました(前出のシミュレーション動画でもこの地域はかなりの波高を見せています。旧安良村のおおよその位置)。
 次は、明和の大津波の慰霊碑が宮良台地(宮良集落北方)にあるとの少ない情報を元に、軽井沢倶楽部ホテルの北側周辺の畑の中を探索。道という道をしらみつぶしに走ること小一時間、周囲を畑に囲まれた小さな森の中に、ようやく目的の慰霊碑を発見しました(直前の入口にブリキの看板があらぬ方向を向いたまま打ち捨てられいた)。
次は、明和の大津波の慰霊碑が宮良台地(宮良集落北方)にあるとの少ない情報を元に、軽井沢倶楽部ホテルの北側周辺の畑の中を探索。道という道をしらみつぶしに走ること小一時間、周囲を畑に囲まれた小さな森の中に、ようやく目的の慰霊碑を発見しました(直前の入口にブリキの看板があらぬ方向を向いたまま打ち捨てられいた)。「明和大津波遭難者慰霊之塔」1983(昭和58)年に建立された(建立当時の写真)。碑文には「午前八時ごろ大地震があり、それが止むと石垣島の東方に雷鳴のような音がとどろき、間もなく外の瀬まで潮が干き、東北東南海上に大波が黒雲のようにひるがえり立ち、たちまた島島村村を襲った。波は三度もくりかえした」と当時の凄まじい津波の様子が記されていました。結果的に島の人口が3分の1まで減少するという未曾有の大災害を語り継ぐ慰霊碑は、今や大きな繁栄を遂げた平穏な石垣の街を、宮良の丘の上から静かに見下ろしていました(地図は文末を参照)。
 海洋地質学者・地震学者の木村政昭・琉球大学名誉教授によると、独自の「時空ダイアグラム」理論で先日(2月27日)の本島近海地震を的中させたそうです(2011年±2:M7.0)。しかも、2009年8月5日の宮古島南方沖(M6.5/宮古島 震度4)、2010年2月7日の波照間島南方沖(M6.6/石垣島 震度3)、2010年3月5日の台湾南部(M6.4)などの発生も予想して的中させたそうです。
海洋地質学者・地震学者の木村政昭・琉球大学名誉教授によると、独自の「時空ダイアグラム」理論で先日(2月27日)の本島近海地震を的中させたそうです(2011年±2:M7.0)。しかも、2009年8月5日の宮古島南方沖(M6.5/宮古島 震度4)、2010年2月7日の波照間島南方沖(M6.6/石垣島 震度3)、2010年3月5日の台湾南部(M6.4)などの発生も予想して的中させたそうです。木村教授の研究では、東海地震(富士山の噴火も)は2011年(±4年)に、東南海地震は2050年頃に、2012年(±3年)には東京直下地震がおこると予想されていました(木村教授の私的な作業仮説として、M6.5以上を予測)。
しかし、木村教授が的中したという地震以外にも沖縄近海(台湾~奄美)では、M6以上の地震が6回ほどおきていますので、まだまだ予知100パーセントというのは難しいように思われますが、これはとても興味深い研究です。
 また最新の調査よると、これまで大規模な地震が起きる可能性が低いとされていた沖縄にも、大地震が発生する可能性の高い、プレートの歪みをためる固着域が本島南方の琉球海溝で発見されました。分析をおこなった琉球大学理学部 中村衛准教授ら研究チームは、この海溝沿いで発生した八重山地震(明和の大津波)の痕跡から、石垣島の南方にも別の固着域が存在する可能性も判明(沖縄沖に巨大地震源 岩板境界、ひずみたまる構造 沖縄沖に大地震の巣/M8級の可能性:asahi.com)。
また最新の調査よると、これまで大規模な地震が起きる可能性が低いとされていた沖縄にも、大地震が発生する可能性の高い、プレートの歪みをためる固着域が本島南方の琉球海溝で発見されました。分析をおこなった琉球大学理学部 中村衛准教授ら研究チームは、この海溝沿いで発生した八重山地震(明和の大津波)の痕跡から、石垣島の南方にも別の固着域が存在する可能性も判明(沖縄沖に巨大地震源 岩板境界、ひずみたまる構造 沖縄沖に大地震の巣/M8級の可能性:asahi.com)。琉球海溝は太平洋側フィリピン海プレートが、琉球列島が乗っているユーラシアプレートに沈み込もうとする、静岡県から四国沖に連なる東海・東南海・南海の地震と同じプレート境界にあたり、木村教授が予測する、2019年(±4年)に沖縄本島近海でM7.3~7.7規模の地震予知にも、大きな信憑性が増したような気がします。
果たして、2020年に開催される第32回夏季オリンピック(ロンドンの次のリオデジャネイロの次のオリンピックですが・・・)を無事に観戦することは出来るでしょうか?。
[明和の大津波]
1771年4月24日(明和八年三月十日)午前8時頃、マグニチュード7.4の地震が石垣島の近海で発生。地震によって発生した巨大津波は、石垣島では85.4メートルにも達したといわれている。
[資料]
琉球大学理学部 中村衛研究室(明和の大津波、本島近海地震、チリ地震津波など資料豊富)
木村政昭ホームページ(地震の発生予知図あり)
八重山の明和大津波 日本近海での歴史上最大級津波災害(pdfで判りやすい資料)
日本の地震活動/沖縄県に被害を及ぼす地震及び地震活動の特徴(沖縄県)[フレームあり]
石垣島の日本一・世界一その3 津波の波の高さ(読み物としても面白い石垣市による資料集)
「バリ石」は「津波石」 伊原間海岸/八重山毎日新聞オンライン(津波石の話題)
石垣島歴史の道を行く2 安良越地を歩く(旧安良村へのレポート)
[関連記事]
明和の大津波-その時宮古は-
(文+写真+編集:モリヤダイスケ)
Posted by あんちーかんちー編集室 at 09:00│Comments(0)
│あんちーな特集